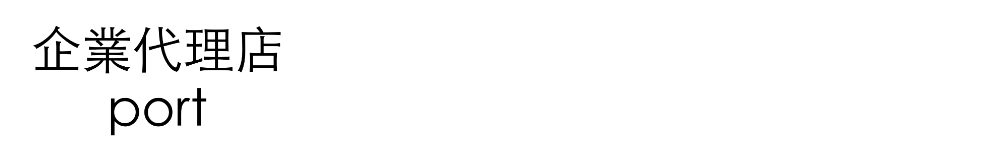先日、以前勤務していた会社の上司であった栗山泰史氏に20年ぶりにお会いした際に、最近の損害保険業界において起こっている出来事について同氏のご意見をお伺いする機会がありました。
そのきっかけで、以前に同氏が執筆された『損害保険事業における「共通化・標準化」の意義と今後の展開』と題するレポートを共有していただきました。
2013年のレポートではありますが、デジタル化が進展しつつある現在においても大変参考になる内容であると思い、本メディアにてもご紹介させていただきます。
企業向け保険の価格調整問題(カルテル疑惑)が取り沙汰されている中だからこそ参考になる部分があるのではないかと考えています。
本記事は栗山氏執筆のInswatch Professional Report【第112号】2013.02.22【損害保険事業における「共通化・標準化」の意義と今後の展開】を、許可を得て転載する記事であり、複数回に分けて掲載をしていきます。
長編となっているため、3分割の第一弾を掲載します。
以下転載部分
はじめに
「共通化・標準化」の大きなうねりが損保業界に生じている。
一般社団法人日本損害保険協会(以下、「損保協会」)の第六次中期基本計画(2012 年度から2014 年度までの3 年間)においても「共通化・標準化の推進による消費者利便の向上と業務効率化」が重点課題の一つとして採り上げられている。
筆者が損保協会に職を得たのは2009 年である。今から数えて、ほんの数年前のその当時でさえ、「共通化・標準化」は、損保業界においてほとんど市民権を得ていない状況であった。
むしろ、保険会社間の競争による個別化の進展と独禁法への抵触の恐れから、「共通化・標準化」は出来る限り狭い範囲に留めるべきという考え方が主流をなしていた。
東日本大震災の体験を経て、今、「共通化・標準化」は、損保業界としての大きな課題となっている。
しかし、実は「共通化・標準化」は決して新しい考え方ではない。
かつて、損保協会の業務の多くは「業界協調」すなわち業務の「共通化・標準化」を実現するためのものであり、各保険会社は基本的にこれを尊重していた。
それが自由化、規制緩和を経て大きく変化し、そのほとんどが廃止されることとなった。
古い「共通化・標準化」は捨て去られ、新たな「共通化・標準化」が再評価され、損保業界の重要な課題として生まれ出ようとしている。
本稿では、「共通化・標準化」を巡る歴史、これが再評価されることとなった背景、そして、今後の展開について述べたい。
1.「共通化・標準化」の前史(1)保険自由化前の「業界協調」
①損保協会の委員会による「業界協調」
保険自由化前の損保業界を振り返るにあたり、損保協会の果たしていた役割と使命について確認しておこう。
損保協会は、2012 年4 月1 日から一般社団法人に改組したが、それまでは、公益社団法人であった。
公益社団法人は、二つの事業を行う。 一つは共益事業、すなわち会員である保険会社のために役に立つ事業である。
もう一つは公益事業、すなわち世の中全体に対して役に立つ事業である。損保協会は、共益事業と公益事業の両方を行う組織であり、この点は、一般社団法人に改組しても変わることはない。
<委員会体制>
保険自由化前、損保協会は共益事業を中心に運営されており、共益事業こそが損保協会のレゾンデートルであった。そして、これを担っていたのが各種の委員会組織である。
保険種類ごとに設置された商品の委員会を中心に、募集制度、損害調査、総務、経理、財務、広報等、業務分野別に委員会が存在した。
そして、損保協会はそれら委員会の事務局を担い、損保協会の組織もまた委員会に即応した体制となっていた。損保協会は、まさに業界協調の場そのものであったのである。
中でも力を発揮していたのは自動車、火災、新種の商品別に設置された委員会であり、商品に関わる基本的なルールの多くが、委員会によって、業界共通のものとして決められていた。
当時、料率算出団体法の下で約款と料率が一律に規制された種目は、自動車・火災・傷害のみであった。
しかし、保険業法の中に独禁法適用除外が設けられていたこともあり、あまり深く独禁法上の問題を吟味することなくその他の種目についても業界委員会を中心として日々の業務が行われていた。
<賠償責任保険の場合>
筆者は、1975 年に当時の安田火災に入社し、1978 年に新種業務部に配属されて賠償責任保険の担当となったが、赴任後しばらく経って損保協会の委員会に出席することとなった。
当時、賠償責任保険で言えば、最上位の委員会は新種保険委員会であり役員クラスが委員に就任していた。
その下に部長クラスの新種業務委員会があり、さらにその下に課長クラスで構成される賠償責任保険専門委員会があった。
そして、その下に約款小委員会、その他数々の小委員会があり、当時の筆者のような「駆け出し」は、小委員会やさらにその下の作業班のメンバーとして業界各社の同じ業務の担当者と深い接点をもつこととなった。
そこでは、それほど大きな歳の差のない先輩から会社の枠を超えた指導を受ける中、約款や料率の基本、あるいはアンダーライティングの基礎や本質を学ぶことができた。
すなわち、同じ会社の他種目の担当者よりも他社の賠償責任保険担当者の方が親しく、また、多くを学ぶ慣習が出来上がっていたのである。
では、このような「仲の良い」環境の下で、賠償責任保険に関する各社間の競争はなかったのであろうか。実は激しい競争が行われていたのである。
賠償責任保険の料率は、圧倒的に多くのリスクが行政の認可に縛られない自由料率の対象であった。
また、約款についても、保険契約者である相手企業のニーズに合わせて個別の特約を2社間の覚書というかたちで次々とつくり上げていかなければ保険は成約に至らない。
すなわち、約款と料率の基本部分において、損保協会の委員会を通じた一定の規律が保たれる一方で、最前線では各社のアイデアやノウハウ、深い知識を競いあう激しい競争が行われていたのである。
<様々な分野の委員会>
こうした損保協会の委員会を通じた業界としての規律、すなわち「共通化・標準化」は、保険商品だけでなく、その他の分野にも広く浸透していた。
損害調査分野では、業界としての標準となる損害調査に関わる各種の考え方を損保協会の委員会を通じてつくり上げていた。
保険の募集・販売分野でも同様に、代理店としての種別と個人資格をベースとしたノンマリン代理店制度が業界の制度として作られ、募集取締法を遵守し、保険契約者に役立つ、質の高い代理店を生み出すことを目指していた。
保険会社や代理店の監査についても同様に、損保協会としての監査制度が設けられていた。
保険会社の経営に関わる重要な事項は大蔵省が検査する一方で、契約規定等の実務に近い部分については、保険会社で長年営業現場を経験してきた各社のベテラン社員がOBになった後、損保協会の監査人に登用されて検査を行う態勢になっていた。
その他、例えば安全防災の分野においても、業界としてのノウハウの蓄積が行われ、各社の経営の効率化に寄与していた。
②「業界協調」の意義と限界
損保協会をベースとした委員会体制によって各社の商品、損害調査、募集、その他多くの分野での協調が実現し、そこで生み出される規律によって、保険の歴史上、繰り返し見られる保険会社間の破滅的な競争が発生し得ない状況がつくり出されていた。
そして、当時の大蔵省は、商品の認可・管理、財産運用等の保険会社の監督、その他種々の行政上の業務を行う上で、損保協会の委員会を上手に活用した。
知識・ノウハウを持った各社社員が英知を結集し徹底的に議論を重ね、一定の妥協を経て生み出される委員会の場での結論は、特定の保険会社に過度に肩入れすることのない中立的な性格を持つため、大蔵省が当時のいわゆる護送船団行政を実施する上での重要な糧となった。
すなわち、損保協会の委員会は、大蔵省が行う護送船団行政の実効性を高めることに貢献し、大手、中小を問わずすべての保険会社に協調の場を提供することに寄与していた。
そしてその結果、保険会社間の弱肉強食の激しい競争は相当程度抑制され、商品戦略や営業政策の歪み、さらには保険会社の破綻による保険契約者の被害が回避される仕組みとなっていたのである。
しかしその一方、保険会社の協調体制が維持されることで、経営の非効率性、商品の画一性、財産運用の保守性等の弊害が生じ、結果的に、保険契約者の利便性が阻害されるという事態が生じていたことも否めない事実であった。
(2)保険自由化による「業界協調」の崩壊
損保協会の委員会をベースとした「業界協調」は、1990 年代の初めころから見直しを求められるようになった。
その動きを、①保険業法の全面改正、②日米保険協議、③独禁法の遵守、④保険会社間の競争激化の4 つに分けて述べたい。
①保険業法の全面改正
1980 年代の終わり頃、わが国にも「自由化・規制緩和」の動きが全産業分野に生じることとなり、金融・保険もその例外ではなかった。
銀行、証券の場合、それまでの規制体系の抜本的な見直しが金融制度調査会の場で行われていた。
すなわち、銀行・証券の相互参入に係る「銀証問題」、普通銀行・長期銀行・信託銀行の在り方に係る「銀銀問題」である。
そして、銀行、証券に保険を加えて銀証保の三位一体で議論するべきという問題意識から、当時の大蔵省の下に1989 年に設置されたのが保険審議会総合部会であった。
後から振り返ると「バブル」と称された過熱景気の下でのカネ余り現象、それを背景としたわが国銀行、証券の海外進出、アメリカを中心に金融に生じたイノベーションの波、それらを背景とした金融各業態間の垣根の低下、こうした状況の中で、金融に携わる各業態は自らのプレゼンスアップを図り、行政もそれを促進した。
損保業界においては積立型保険の大きな伸びを契機に生保への進出に大きな期待が生じ、生保は金融事業への進出を強く願っていた。
保険業法は、こうした動きの中で1996 年に56 年ぶりに改正され施行されることになったのである。
そして、保険業法の改正と、後に記す日米保険協議の合意の2つの流れを融合する位置づけとなるのが、1996 年11 月に橋本政権の下で提唱された「金融ビッグバン」と、これを具体化した1998 年6 月の金融システム改革法の成立である。
損保においては、こうした一連の流れの中で、自由化が制度的に進展した。
具体的には、算定会制度の改革を中心とする商品・料率の自由化、新たな保険販売制度の導入、生損保の相互参入等業態間の相互乗り入れ、保険会社の破綻を想定した各種の制度整備等である。
そして、こうした法的な改革によって、それまで業界として培ってきた協調態勢が大きく壊れていくことになるのである。
すなわち、護送船団行政をベースとした「業界協調」から、保険会社各社の個別戦略による差異化を図る方向に各社は大きく舵を切ることになった。
自由化の根底にある考え方は、公的規制の緩和による民間活力の活用である。
行政が規制をベースに世の中をよりよい方向に持って行くという考え方は、アメリカのレーガン大統領、イギリスのサッチャー首相の登場に代表される新しい動きによって大きく変化することとなった。
保険事業でいえば、それまでの護送船団行政による「業界協調」とそれによる業界としての活力の低下や保険契約者利便の低下に対し、自由化による競争促進によって個々の保険会社と業界全体の活性化が図られることとなった。
ちなみに、自由化は何をやっても構わないというルール不在の状態を意味するものではない。
後退するのは公的規制であり、消費者や保険契約者、株主等の保護は一層強化され、公的規制に代わり民間自らによる自己規制が必要になる。
この結果が、コーポレートガバナンス、ディスクロージャー、コンプライアンス等の強化であり、これを怠った場合、業務停止等の厳しい制裁処置が課せられる。
そして、自由化前は「箸の上げ下げまで規制する」と揶揄された公的規制はソルベンシーマージン規制や破綻処理システムの設置など限定的なところに後退することになった。
②日米保険協議
保険業法の改正による競争促進に伴いそれまでの「業界協調」は大きく後退することになったが、この進展をラディカルなものにしたのがグローバルな動きである。
保険は長くローカルマーケット(国内に限定される市場)を中心に運営されてきた。
例えばある人が自分の自動車保険を購入する場合、アメリカの保険会社から直接購入することはできない。
つまり、通常の商品のように「輸入」ができないのである。
これはわが国の保険業法による規制の結果であり、逆に日本の保険会社の「輸出」も多くの場合、各国の規制によって禁止されている。
二度にわたる世界大戦の反省から設けられた多国間協議GATTの場では、関税を中心に「モノ」の貿易に関する議論が行なわれてきたが、ウルグアイラウンド以降、「サービス」の自由化が議論されることとなり、「サービス」の一環として、金融、保険分野の自由化も取り上げられることとなった。
1986 年に始まったGATTウルグアイラウンドにおいて行われた保険自由化の議論は、まさに保険の輸出入をどう実現するかという「クロスボーダー取引」を巡る議論であった。
そして、この結果、GATTがWTOに衣更えする中で、マリン、航空、国際間輸送(M.A.T)の3分野に関しては国境を越えた保険取引の自由化が実現した。
<日米保険協議における主要議題>
日本国内(unilateral)における保険自由化に向けた保険業法改正の動き、多国間(multilateral)協議としてのGATT、そして、これらと機を同じくして日米2国間(bilateral)で行われたのが日米保険協議である。
1996 年12 月に決着した「日米保険協議」は、日米間の貿易摩擦の激化に伴い自動車、政府調達、保険の優先3分野を筆頭に、1993 年7 月以降、様々な産業分野別に行われた「日米包括経済協議」の一つである。
そしてこの協議は、これに先立つ「日米構造協議」で議論された系列取引や株式の持ち合い、独禁政策等、日本の経済・産業構造に関わる主要特性の見直しと相まって、その後のわが国の保険制度を大きく変える上で、非常に大きな要因になるものであった。
日米保険協議において様々なことが協議の対象になったが、大きな区分としては主要分野の規制緩和と第三分野における参入条件の二つを挙げることができる。
主要分野の規制緩和に関しては、算定会制度の全面見直しの結果、料率の使用義務が廃止されることになり、またリスク細分型自動車保険の導入が決まった。
一方、第三分野の生損保相互参入に関しては、生損保本体での相互参入はもとより、子会社による扱いに関しても制限が加えられることとなった。
それらは1998 年6 月の金融システム改革法に反映し、その後、2001年頃まで順次、具体的なかたちで実現することになった。
これらが、日米保険協議が保険自由化に与えた大きな制度面での影響である。
<目立たなかった議題>
ところで、日米保険協議におけるアメリカ側の要求のなかには、日本の損保業界に大きな影響を及ぼすにも拘らず、ほとんど表に出なかったものがあった。
それは、保険商品や募集、保険会社や代理店への監査に関する業界としての協調や共同の仕組みに関連する要求であった。
例えば当時、ある保険会社が新商品を開発した場合、ある程度の期間を過ぎればその内容を他の保険会社に開示し、最終的には販売を望む保険会社はどこでもその商品を売り出すことが可能になるという「慣行」があった。
この慣行に対して、アメリカは「日本には新商品の他社への開示という制度があるだろう。それは競争促進の観点から止めるべきだ」と要求してきた。
この開示という慣行は、保険業法等の法律や、通達行政として批判の対象となった行政の「通達」にさえ明示されていないものであった。
従って、アメリカの要求に対して当時の大蔵省も日本の保険業界も、「開示という制度は存在しない」としか反論の仕様がなかった。
そして、その反論をベースにアメリカから「開示制度はないのだな」と念押しをされ、慣行として行われていた開示は結果的に消滅することとなった。
商品、募集、損害調査の分野には、行政当局による通達のみを根拠とするものや、損保業界内の判断によって長きにわたり阿吽の呼吸で設けていた業界共通基盤があったが、これらは法的裏づけのない「慣行」であったために、日米保険協議により、表立って議論されることなく廃止されることになった。
日米保険協議は、表舞台に堂々と現れた法的制度面の改革だけでなく、裏舞台で、長い間業界として持ち続けた「慣行」という「業界協調」を廃止することにもつながったと言えるだろう。
もちろん言うまでもないことだが、当時の法的に不透明な「業界協調」は決して許されるものではなく、ましてや今の時代において、不透明な「業界協調」が復活することは絶対にあり得ないことを強く自覚しなければならない。
③独占禁止法の遵守
「業界協調」が大きな見直しを迫られることとなった3つ目の要因は、独占禁止法(以下、「独禁法」)の遵守である。
<日米構造協議>
実は、独禁法を巡る動きに関してもアメリカの力によるところが非常に大きい。
戦後の日本経済の発展にともなって歴史的に順次、様々な分野で貿易摩擦が起こるようになった。
これに対し、アメリカは、例えば繊維製品など産業分野別にダンピングの停止や数量制限等の要求をしていたが、こうした対応に根本的な変化が生じたのが1989 年に始まった「日米構造協議」である。
この協議におけるアメリカの視点は、「日本の問題は、自動車や繊維など産業別の問題ではなく、欧米とは異質の経済・社会体制にある。
例えば、独禁法もその一つで、第二次大戦後、法は制定されたが、日本の社会においてそれは形骸化している」というようなものであった。
そして、独禁政策だけではなく、株式の持ち合い、系列取引などの日本の経済社会構造上の特色に着目し、これに徹底的にメスを入れることを試みたのである。
これが日米包括経済協議に先立つ日米構造協議であった。
当時、日本国内でこれを高く評価する動きがあり、日米構造協議を、明治維新、敗戦に続く第三の開国と位置づける見方さえ存在した。
当然のことながら、独禁法を司る公正取引委員会(以下、「公取委)は、独禁法の適用強化の方向に大きく舵を切ることとなり、このような中で、損保業界を大きく揺るがすこととなったのが「日本機械保険連盟事件」である。
<日本機械保険連盟事件の影響>
日本機械保険連盟は、1956 年に機械保険と組立保険に関する保険会社の事業者団体として設立され、会員に対する技術援助と再保険に関する共同処理を行うことで同保険の普及に貢献することを目的としていた。
これが、同保険の料率に関するカルテル行為を行ったという理由で独禁法違反を問われ、1997 年に解散するに至ったのが「日本機械保険連盟事件」である。
損保業界は同連盟の解散だけでなく、最高裁まで争ったものの54 億円を超える課徴金を支払うこととなった。
この事件は、業界の歴史に残る大きな汚点になると同時に、業界全体に、共同で何かを実施することに極めて慎重にならざるをえない状況を作り出した。
中でも損保協会の委員会をベースに実施していた多くの共益事業が廃止されることになり、損保協会は会員会社に便益を提供するという共益事業から、世の中全体を見据えた公益事業へと、業務の中身を大きくシフトすることになった。
このようにして、損保業界は、「業界協調」の主要な場を失うこととなったのである。
④保険会社間の競争激化
保険業法の改正による自由化、これの進展に一層の拍車をかけた日米保険協議、さらに損保業界を揺るがした日本機械保険連盟事件による独禁法問題、これらを要因にして、それまで業界協調を重視してきた保険会社はそのスタンスを大きく競争に向かって変えることになった。
競争の激化は、当初、商品・料率の自由化に伴い保険商品の分野で生じ、ダイレクト系保険会社によるリスク細分型自動車保険による大幅な保険料割引、大手保険会社を中心にした特約の多様化による商品の差別化などが行われた。
その頃、世の中全体に株主重視の動きが生じ、保険会社はこの結果、利益を増大させ、株主への手厚い配当と株価の上昇を強いられることとなった。
商品を巡る競争によって、保険料が下げ基調にある状況の中で利益を確保するための唯一の道は経費の削減、すなわちローコストオペレーションである。
そして、この具体的な施策が保険募集における保険代理店と営業職員の二重構造の解消であった。
そして、ローコストオペレーションの進展は、最終的に2000 年代初頭の業界再編を経て3 メガ損保の登場にまでつながることとなった。
このような保険会社間の競争激化の中で、各社は、商品のみならず損害調査、事務システム、募集、代理店政策等あらゆる分野を競争領域に位置付け、本来的に必要な「業界協調」、すなわち「共通化・標準化」は、法律の要求など必要最小限の範囲に止まるという状態になって行った。
転載部分以上
次回予告
次回は業界協調が再評価されることになった背景や、諸外国の事例を紹介します。
↓次回はこちら
②損害保険事業における「共通化・標準化」の意義と今後の展開 業界協調の再評価と諸外国の事例 | 企業代理店port (kigyodairiten-port.com)
この記事が「参考になった」「ためになった」と感じていただけたら、メール会員登録をよろしくお願いします!
メール会員登録はこちら! | 企業代理店port (kigyodairiten-port.com)